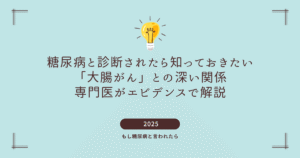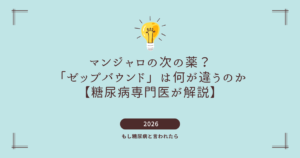糖尿病神経障害とは? 専門医が解説する正しい理解と早期対策
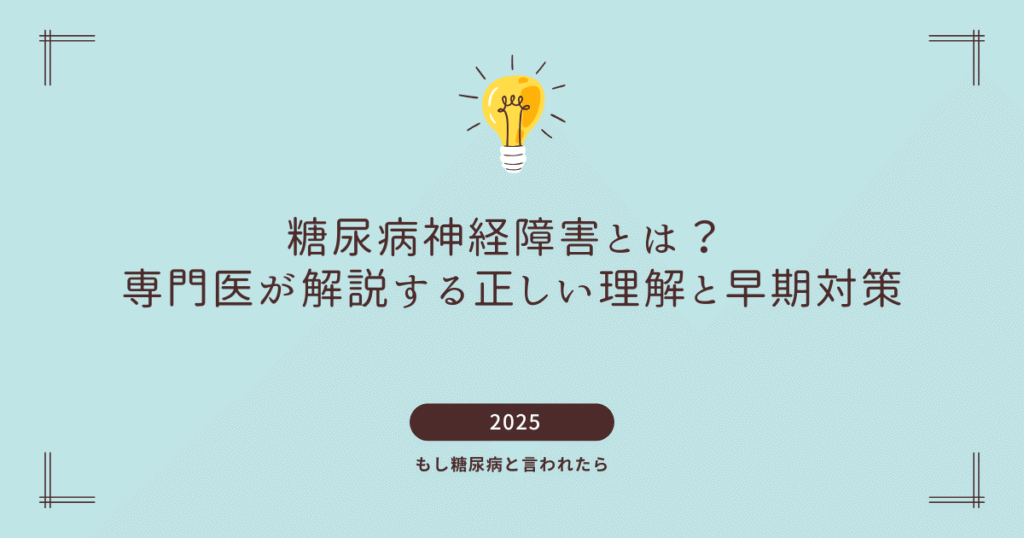
糖尿病と診断された皆様へ

「糖尿病ですね」「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が高いです」
健康診断や病院でこのように告げられ、大きなショックと不安を感じていらっしゃるかもしれません。ご家族やご友人に糖尿病の方がいらっしゃらない場合、何をどうすれば良いのか、何を恐れたら良いのかさえ分からず、混乱している方も多いでしょう。
多くの人が「糖尿病=怖い」と感じる理由、それは「合併症(がっぺいしょう)」の存在です。糖尿病は、血糖値が高い状態が続くことで、全身の血管や神経がダメージを受けてしまう病気です。
合併症には様々な種類がありますが、今回はその中でも最も早く、そして最も多く見られる「糖尿病神経障害」について、詳しく解説します。
この記事では、なぜ神経障害が起こるのか、どのような症状があるのか、そして科学的根拠(エビデンス)に基づいた最新の対策について、専門医の視点からわかりやすくお話しします。
糖尿病神経障害とは?
「神経障害」と聞いても、ピンとこないかもしれません。簡単に言えば、「高すぎる血糖値が、全身に張り巡らされた神経をじわじわと傷つけてしまう」状態です。
私たちの体には、大きく分けて2種類の神経があります。糖尿病は、その両方に影響を及ぼす可能性があります。

末梢神経障害
これは、手足の先に行く「感覚」や「運動」を司る神経の障害です。症状は以下の通りです。
- 足先の違和感: 最も多い初期症状です。「足の裏に一枚紙が貼ってある感じ」「砂利の上を歩いている感じ」と表現されることもあります。
- しびれ・痛み: 「ピリピリ」「ジンジン」としたしびれや、針で刺されるような痛みが出ることがあります。
- 感覚の麻痺: 進行すると、逆に感覚が鈍くなります。熱さや冷たさ、痛みに気づきにくくなります。
なかでも、感覚が鈍くなることは、最も恐ろい状態と考えられます。
例えば、靴擦れができても気づかない。熱いお風呂に足を入れても平気で、火傷(やけど)をしてしまう。小さな傷に気づかないまま放置し、そこから細菌が入り込む。
その結果、傷が化膿して「壊疽(えそ)」という状態になり、最悪の場合、足の指や足を切断しなければならなくなるケースがあります。これが、糖尿病神経障害が「怖い」と言われる大きな理由の一つです。

またひとたび症状が出てしまうと、「治す」ことは困難で、鎮痛薬で痛みをコントロールするしかなくなってしまいます。
自律神経障害(じりつしんけいしょうがい)
自律神経は、私たちが意識しなくても心臓や胃腸、血圧、体温などを自動的に調整してくれる、非常に重要な神経です。この神経が障害されると、全身に様々な不調が現れます。
- 立ちくらみ(起立性低血圧): 急に立ち上がった時に、血圧がうまく調整できず、ふらついたり、めまいが起きたりします。
- 胃腸の不調(胃不全麻痺): 胃の動きが悪くなり、食後に胃がもたれたり、吐き気がしたりします。
- 便通異常: 頑固な便秘になったり、逆にひどい下痢を繰り返したりします。
- 排尿障害: 膀胱に尿が溜まっても尿意を感じにくくなったり(残尿)、頻尿になったりします。
- 発汗異常: 暑くても汗をかきにくくなったり、逆に食事中に顔や上半身だけ異常に汗をかいたりします。
- 勃起障害(ED): 男性の場合、自律神経の障害が原因で起こることがあります。
特に注意が必要なのが「無自覚性低血糖」です。通常、低血糖になると冷や汗、動悸、手の震えといった警告サインが出ます。しかし、自律神経が障害されると、このサインが出にくくなります。結果として、重症の低血糖(意識障害や昏睡)に陥るまで気づかない危険性があるのです。
エビデンスの紹介:血糖管理の重要性
「本当に血糖値を下げるだけで、糖尿病神経障害を防げるの?」と疑問に思うかもしれません。ここで、私たちの治療方針の根幹となる、いくつかの重要な科学的根拠(エビデンス)をご紹介します。
神経障害の有病率
糖尿病患者さんのうち、どのくらいの方が神経障害を持っているのでしょうか。アメリカ糖尿病学会(ADA)のポジション・ステートメントによると、糖尿病患者さんの約30%〜50%が何らかの神経障害を有していると報告されています1。これは決して他人事ではない数字です。
厳格な血糖管理の効果 (DCCT/EDIC研究)
これは1型糖尿病の患者さんを対象とした、歴史的に非常に有名な大規模研究です2。
この研究では、患者さんを「従来通りの血糖管理を行うグループ」と、「HbA1cをできるだけ正常に近づけるよう厳格に管理するグループ」に分けました。
その結果、厳格に血糖管理を行ったグループは、従来通りのグループに比べ、糖尿病神経障害の発症リスクが約60%も減少しました。さらに驚くべきことに、この研究(DCCT)が終了した後も追跡調査(EDIC)が続けられ、早期から厳格に管理した効果は、10年以上経っても持続することが分かりました。
2型糖尿病でも効果は同じ (UKPDS研究)
では、日本の糖尿病患者さんの大多数を占める2型糖尿病ではどうでしょうか。
イギリスで行われた大規模研究(UKPDS)がその答えを示しています [3]。この研究でも、診断初期から血糖値を厳格に管理したグループは、そうでないグループに比べ、神経障害を含む細小血管合併症(網膜症や腎症も含む)の発症が有意に(統計的に意味があるレベルで)減少しました。
これらの研究が私たち専門医に教えてくれることは、たった一つです。
「診断された時点から、血糖値を良好にコントロールし続けること。それが、神経障害を予防し、進行を食い止めるための最も強力で、最も確実な方法である」ということです。
専門医の視点からのアドバイス
糖尿病と診断され、動揺している今だからこそ、知っておいてほしい「今日からできる対策」があります。
1. 血糖コントロール(HbA1c)
これが全ての基本であり、最も重要です。まずは主治医と相談し、あなたの年齢、他の病気の有無、ライフスタイルに合わせたHbA1cの目標値を決めましょう。
一般的には「7.0%未満」を目指すことが多いですが、焦る必要はありません。大切なのは、昨日より今日、今日より明日と、少しずつでも改善させていく意識です。食事療法や運動療法、必要であればお薬の力を借りながら、目標に向かって進みましょう。
2. 毎日の「フットケア」(足の観察)
神経障害が進行すると、足の感覚が鈍くなります。そのため、自分自身で足を守る習慣(フットケア)が不可欠です。
- 毎日、足を見ましょう: お風呂上がりなどに、足の裏、指の間、爪などをしっかり観察します。
- チェックポイント:
- 小さな傷、切り傷、水ぶくれはないか?
- 靴擦れができていないか?
- 皮膚が赤くなったり、硬くなったり(タコ、ウオノメ)していないか?
- 爪が食い込んだり(巻き爪)、変色したりしていないか?
- 清潔と保湿: 足は毎日洗い、清潔に保ちましょう。ただし、洗いすぎは禁物です。洗った後はよく乾かし、乾燥している場合は保湿クリームを塗りましょう。
- 靴選び: サイズが合わない靴は、靴擦れやタコの原因になります。自分の足に合った、クッション性のある靴を選びましょう。
もし見えにくい場合は、鏡を使ったり、ご家族に協力してもらったりしてください。小さな異常でも、早めに見つけて主治医や看護師に相談することが、足の切断を防ぐ鍵となります。
3. 禁煙
もし喫煙されているなら、禁煙は必須です。タバコは血管を収縮させ、血流を著しく悪化させます。これは、神経障害を急速に悪化させる最大の要因の一つです。
4. 症状への対処
すでに「しびれ」や「痛み」があり、日常生活に支障が出ている場合、それを和らげるお薬もあります。血糖コントロールとは別に、症状を緩和する治療も可能です。我慢せずに、必ず主治医に相談してください。
正しい知識が未来を守る
糖尿病神経障害は、高血糖が続くことで、感覚や内臓の働きを司る神経が傷ついてしまう合併症です。足のしびれや感覚の麻痺、立ちくらみや胃もたれなど、その症状は多岐にわたります。
しかし、本日ご紹介したエビデンスが示す通り、この合併症は「予防できる」ものであり、早期であれば「改善も期待できる」ものです。
その最大の武器は、診断された「今」、この瞬間から始める良好な血糖コントロールと、ご自身の足を守るフットケアの習慣です。
糖尿病と診断された不安は、専門医である私も痛いほど理解しています。しかし、その不安を「正しく知る」エネルギーに変えてください。私たちは、皆様が合併症に苦しむことなく、健やかな毎日を送れるよう、全力でサポートします。
一人で抱え込まず、私たち医療スタッフと一緒に、一歩ずつ進んでいきましょう。
参考文献
- Diabetes Care. 2017 Jan;40(1):136-154.
- Diabetes Care. 2014;37(1):31-8.
- Lancet. 1998 Sep 12;352(9131):837-53.
関連記事
- 糖尿病とコレステロール
- 脂肪肝とは?糖尿病と脂肪肝のかかわり
- 【医師監修】糖尿病でも安心!1週間の食事メニュー例と続けるコツ
- 【専門医が解説】コーヒーは糖尿病の味方?最新研究が示す驚きの効果と正しい飲み方
- HbA1cってなに?数値の意味と注意点

この記事を書いた人
都内の総合病院で糖尿病や内分泌疾患を専門に診療している医師です。総合内科専門医/糖尿病専門医/内分泌代謝科専門医/医学博士。年間2000人以上の糖尿病患者さんを診察しながら、学会発表や研究活動も行っています。このブログでは、日々の診療で感じた「患者さんが本当に知りたいこと」「わかりづらい医療情報をわかりやすく伝えること」を大切にしています。正しい知識を知ることが、安心への第一歩になりますように。