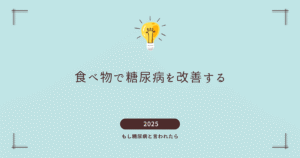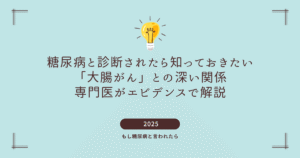糖尿病性腎症の透析はつらい?未来を変えるために知っておきたいこと
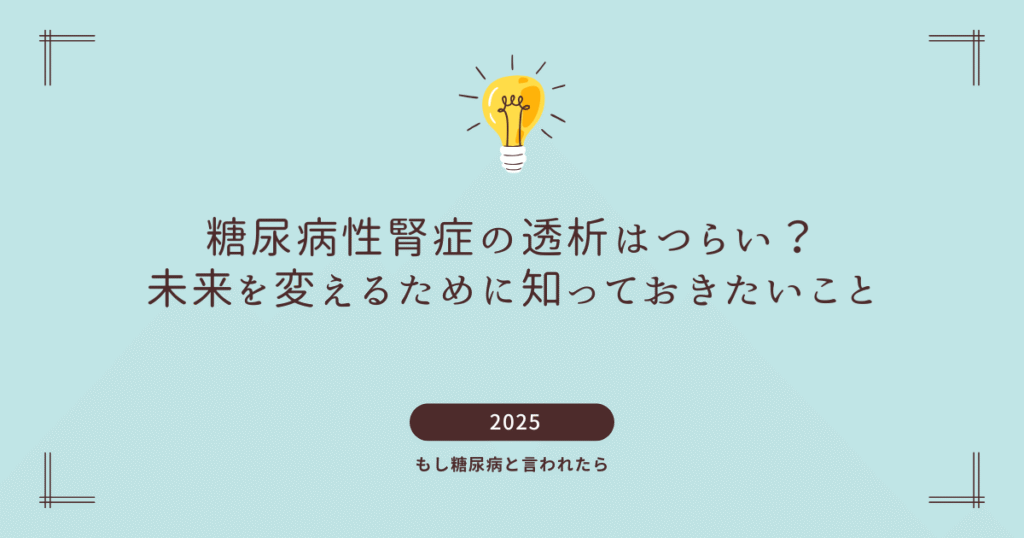
「糖尿病です」と医師から告げられたとき、多くの方が将来への不安を感じます。特に、「もしかしたら、いつか透析が必要になるのかもしれない…」という心配は、心に重くのしかかるものでしょう。インターネットで検索すると、透析治療の大変さばかりが目につき、ますます不安が募るかもしれません。
しかし、立ち止まってください。糖尿病と診断されたからといって、誰もが透析に至るわけではありません。むしろ、早い段階で正しい知識を身につけ、適切な治療を始めることで、透析を回避できる可能性は十分にあります。
この記事では、糖尿病専門医の視点から、透析治療の現実と、最も重要な「透析を回避するための具体的な方法」を、科学的な根拠(エビデンス)に基づいて詳しく解説していきます。あなたの今の行動が、10年後、20年後の未来を大きく変える力を持っています。ぜひ、最後までお読みください。
なぜ糖尿病で透析が必要になるのか?

まず、基本から理解しましょう。私たちの体には「腎臓」という、そら豆のような形をした臓器が2つあります。腎臓は、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排泄する、高性能なフィルターの役割を担っています。
糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)が多くなりすぎる病気です。この高血糖の状態が長く続くと、腎臓のフィルター機能を担う非常に細い血管(糸球体)が傷ついてしまいます。初めのうちは、フィルターの目が粗くなり、本来は体に必要なタンパク質(アルブミン)が尿に漏れ出てきます。これが糖尿病性腎症の初期サインです。
さらに進行すると、フィルターはどんどん目詰まりを起こし、硬くなっていきます。そして最終的には、老廃物をろ過する能力をほとんど失ってしまうのです。この状態を「末期腎不全」と呼びます。
腎臓が機能しなくなると、体の中に毒素や余分な水分が溜まり、尿毒症という命に関わる状態になります。そこで、腎臓の代わりとなって血液をきれいにする治療、それが「人工透析」です。
「透析はつらい」と言われる理由
では、透析治療は具体的にどのようなもので、なぜ「つらい」と言われるのでしょうか。透析にはいくつかの種類がありますが、最も一般的な「血液透析」を例にご説明します。
- 時間的な拘束: 血液透析は、一般的に週に3回、1回の治療に4〜5時間ほどかかります。病院への移動時間を含めると、生活の多くの時間を治療に費やすことになります。これにより、仕事や旅行、趣味などが大きく制限されることがあります。
- シャント手術: 透析を始める前に、腕の血管(動脈と静脈)をつなぎ合わせ、透析に必要な血液量を確保するための「シャント」という出入り口を作る手術が必要です。シャントは透析のたびに太い針を2本刺すため、痛みを伴うこともあります。
- 身体的な負担: 透析中は長時間ベッドの上で過ごします。治療の過程で血圧が変動したり、だるさや疲れを感じたりすることもあります。
- 厳しい食事・水分制限: 腎臓の機能が失われているため、塩分、カリウム、リン、そして水分の摂取量を厳しく管理する必要があります。食べたいものが食べられず、飲みたいものが飲めないというストレスは、精神的に大きな負担となります。
- 合併症のリスク: 透析治療を長期間続けると、心血管系の病気や骨のもろさ、感染症など、さまざまな合併症のリスクが高まります。
このように、透析は命を維持するために不可欠な治療ですが、生活の質(QOL)に大きな影響を与えることも事実です。日本透析医学会の統計調査によると、透析導入後の5年生存率は約60%と報告されており、決して楽な道のりではないことがデータからも示唆されています1。
透析は予防できるというエビデンス
ここまで読むと、不安がさらに大きくなったかもしれません。しかし、ここからが最も重要なポイントです。数多くの研究が、「適切な治療によって腎症の進行は食い止められ、透析導入を大幅に遅らせたり、回避したりできる」ことを証明しています。
エビデンス①:厳格な血糖コントロールの効果
糖尿病治療の基本は、血糖値を良好に保つことです。これが腎臓を守る上でいかに重要かを示したのが、有名な「DCCT/EDIC研究」です2。この大規模な研究では、1型糖尿病の患者さんを対象に、血糖値を厳格に管理するグループと、従来通りの管理をするグループを比較しました。その結果、厳格な血糖管理を行ったグループでは、腎症の発症リスクが大幅に低下することが示されました。さらに、この効果は研究終了後も20年以上にわたって持続することが確認されています。これは、早期からの良好な血糖コントロールが、将来の腎臓を長く守り続ける「遺産(レガシー)効果」を持つことを意味します。
エビデンス②:血圧管理の重要性
高血圧は、高血糖と並んで腎臓に大きなダメージを与える要因です。特に糖尿病患者さんにおいては、血圧の管理が極めて重要になります。「RENAAL研究」や「IDNT研究」といった有名な臨床試験では、ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)と呼ばれる種類の降圧薬が、血圧を下げる効果に加えて、腎臓を保護する特別な作用を持ち、透析導入のリスクを著しく減少させることが証明されました3。現在、糖尿病性腎症の治療では、このタイプの薬が第一選択薬として広く使われています。
エビデンス③:新しい治療薬SGLT2阻害薬の登場
近年、糖尿病治療は目覚ましい進歩を遂げています。その中でも特に注目されているのが、「SGLT2阻害薬」という新しいタイプの薬です。この薬は、尿中に糖を排出させることで血糖値を下げるだけでなく、腎臓にかかる負担を軽減し、腎機能を保護する強力な効果があることが分かってきました。
「CREDENCE試験」という研究では、SGLT2阻害薬(カナグリフロジン)を服用したグループは、プラセボ(偽薬)を服用したグループに比べて、末期腎不全への進行や腎臓が原因の死亡リスクが34%も減少するという画期的な結果が示されました4。同様の効果は「DAPA-CKD試験」など他のSGLT2阻害薬でも確認されており5、今やこの薬は糖尿病性腎症の治療に欠かせない存在となっています。
【専門医からのアドバイス】今日から始める、腎臓を守るための5つのアクション
これらの確かなエビデンスに基づき、透析を回避するために今日から実践できる具体的な行動をお伝えします。
- 血糖コントロールを徹底する (HbA1c < 7.0%)
まずは、過去1〜2ヶ月の血糖の平均値を示すヘモグロビンA1c(HbA1c)を7.0%未満に保つことを目標にしましょう。食事療法と運動療法が基本ですが、必要に応じて最適な薬物療法を主治医と相談してください。 - 血圧を厳格に管理する (130/80 mmHg未満)
家庭で血圧を測定する習慣をつけ、診察室血圧で130/80 mmHg未満を目指します。特に、前述のRAS阻害薬(ARBやACE阻害薬)は腎保護効果が高いため、積極的に使用が検討されます。 - 食事療法を見直す(特に減塩)
塩分の摂りすぎは血圧を上昇させ、腎臓に直接的な負担をかけます。1日の塩分摂取量を6g未満に抑えることを目指しましょう。だしや香辛料をうまく使う、加工食品を避けるなどの工夫が有効です。腎症が進行した場合は、タンパク質の制限が必要になることもありますので、必ず医師や管理栄養士の指導を受けてください。 - 最適な薬物療法を受ける
近年、腎臓を守る効果が科学的に証明された素晴らしい薬が次々と登場しています。ご自身の状態に合った最新の治療が受けられるよう、定期的に主治医と治療方針について話し合うことが大切です。 - 定期的な検査を欠かさない
糖尿病性腎症は、初期には自覚症状が全くありません。静かに進行するため、「サイレントキラー」とも呼ばれます。しかし、定期的に尿検査(尿中アルブミン測定)と血液検査(eGFR測定)を受けることで、腎臓のダメージを早期に発見することができます。早期に発見し、治療を強化すれば、進行を食い止めることは十分に可能です。
未来はあなたの手の中に
糖尿病性腎症による透析治療は、大きな負担を伴う厳しい治療です。しかし、この記事で解説してきたように、透析は決して避けられない運命ではありません。
科学的な根拠に基づいた適切な治療を早期から粘り強く続けることが肝要です。腎臓の機能を守り、透析を回避できる可能性は飛躍的に高まります。糖尿病と診断された今こそが、あなたの未来を変えるためのスタートラインです。
不安な気持ちを一人で抱え込まず、主治医や医療スタッフを信頼し、一緒に治療に取り組んでいきましょう。今日のあなたの小さな一歩が、健康で豊かな未来へとつながっています。
参考文献
- Ther Apher Dial. 2015 Dec;19(6):540-74.
- N Engl J Med. 2005 Dec 22;353(25):2643-53.
- N Engl J Med. 2001 Sep 20;345(12):861-9.
- N Engl J Med. 2019 Jun 13;380(24):2295-2306.
- N Engl J Med. 2020 Oct 8;383(15):1436-1446.

この記事を書いた人
都内の総合病院で糖尿病や内分泌疾患を専門に診療している医師です。総合内科専門医/糖尿病専門医/内分泌代謝科専門医/医学博士。年間2000人以上の糖尿病患者さんを診察しながら、学会発表や研究活動も行っています。このブログでは、日々の診療で感じた「患者さんが本当に知りたいこと」「わかりづらい医療情報をわかりやすく伝えること」を大切にしています。正しい知識を知ることが、安心への第一歩になりますように。