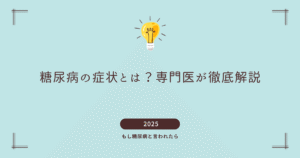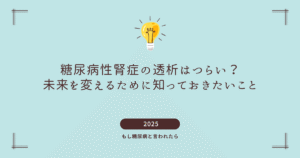食べ物で糖尿病を改善する
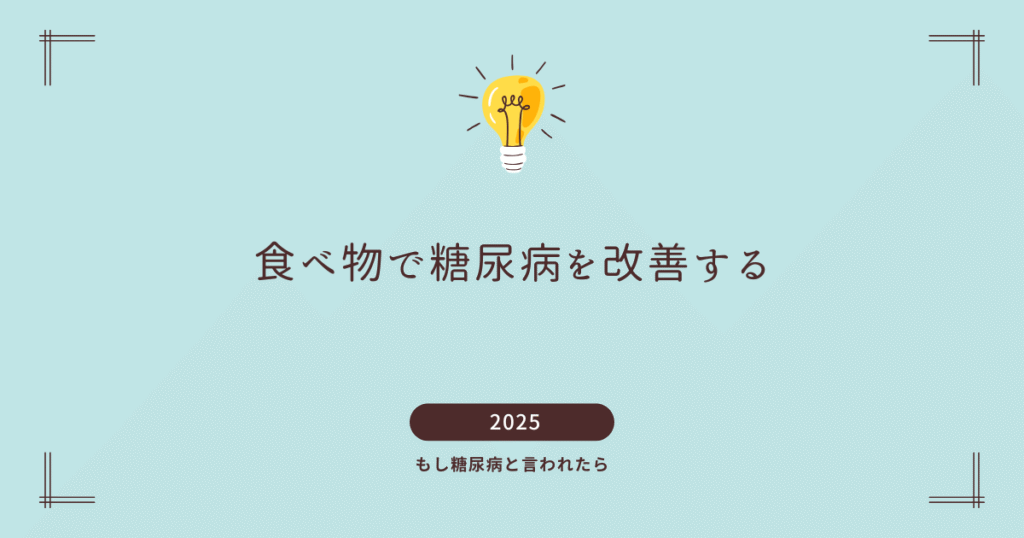
本記事にはアフィリエイト広告を利用しています
導入
「あなたは糖尿病です」
医師からそう告げられ、頭が真っ白になったかもしれません。
今後の食事はどうすれば良いのか。
ラーメンやステーキは一生食べられない?野菜だけの食事にしないとだめ?
そのような不安でいっぱいなのではないでしょうか。しかし、過度に心配する必要はありません。実は、日々の食事を少し工夫するだけで、血糖値のコントロールは大きく改善できる可能性があるのです。
食事療法は、糖尿病治療の基本であり、最も重要な柱の一つです。
そして、その効果は多くの科学的な研究によって裏付けられています。
この記事では、どのような食べ物が血糖コントロールに有効なのか、その科学的な根拠(エビデンス)を交えながら、専門家の視点で詳しく解説していきます。正しい知識を身につけ、日々の食事に活かしていきましょう。
なぜ「食べ物」で血糖値が良くなるのか?
そもそも、なぜ食べ物が血糖値に影響を与えるのでしょうか。その仕組みを簡単に理解することから始めましょう。
食事をすると、食べ物に含まれる「糖質」が消化・吸収され、ブドウ糖として血液中に入ります。これが「血糖」です。血糖値が上がると、すい臓から「インスリン」というホルモンが分泌されます。インスリンは、血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませ、エネルギーとして利用させる働きをします。これにより、血糖値は正常な範囲に保たれます。
しかし、糖尿病(特に2型糖尿病)では、インスリンの分泌が不足したり、インスリンが効きにくくなったり(インスリン抵抗性)しています。その結果、食後に血糖値が上がりすぎてしまうのです。
したがって、血糖コントロールを良くするためには、食事の工夫が不可欠です。具体的には、血糖値を急激に上げない食べ物を選んだり、インスリンの働きを助ける食べ物を取り入れたりすることが重要になります。そのためのキーワードが「低GI」と「食物繊維」です。
- GI(グリセミック・インデックス)とは? GIとは、食後の血糖値の上昇度合いを示す指標です。この値が低い「低GI食品」は、糖質の吸収が穏やかで、血糖値の急上昇を抑えることができます。例えば、白米よりも玄米や全粒粉パンの方が低GIです。
- 食物繊維の力 食物繊維、特に水に溶けやすい「水溶性食物繊維」は、小腸での糖質の吸収を遅らせる働きがあります。これにより、食後の血糖値の上昇が緩やかになります。野菜やきのこ、海藻類に豊富に含まれています。
エビデンスが示す!血糖コントロールに役立つ食べ物
ここでは、血糖値の改善効果が科学的に示されている具体的な食べ物や食事パターンを、研究報告とともに紹介します。
食物繊維が豊富な「野菜」と「豆類」
野菜、特にほうれん草や小松菜などの葉物野菜は、食物繊維が豊富で低カロリーです。また、大豆やひよこ豆などの豆類も、良質なタンパク質と食物繊維を多く含み、食後の血糖上昇を抑える効果が期待できます。
ある研究では、豆類の摂取が2型糖尿病患者の血糖コントロールを有意に改善することが示されました。具体的には、豆類を多く摂取したグループは、そうでないグループに比べて、血糖値の長期的な指標であるHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が低下したと報告されています1。これは、豆類が持つ豊富な食物繊維と低いGI値によるものと考えられます。
実際に食事だけで十分な食物繊維をとるのは難しい場合があります。そんなときに役立つのが、サプリや粉末タイプの補助食品です👇👇👇
| 難消化性デキストリン (スーパー即溶顆粒) 2kg 食物繊維 ダイエット ダイエタリーファイバー 微顆粒品 非遺伝子組換え 難消化性 デキストリン 水溶性食物繊維 粉末 パウダー できすとりん 糖質制限 ロハスタイル LOHAStyle 価格:3,680円(税込、送料無料) (2025/9/11時点) 楽天で購入 |
精製されていない「全粒穀物」
主食を選ぶなら、白米や白いパンよりも、玄米、大麦、全粒粉パン、オートミールといった「全粒穀物」が推奨されます。これらは精製されていないため、食物繊維やマグネシウムなどのミネラルが豊富です。
2型糖尿病患者を対象とした複数の研究を統合したメタアナリシス(質の高い研究手法)によると、全粒穀物の摂取は空腹時血糖値とHbA1cの改善に関連していることが確認されました2。日々の主食を置き換えることから始めてみるのが良いでしょう。
間食に最適な「ナッツ類」
アーモンドやクルミなどのナッツ類は、良質な脂質(不飽和脂肪酸)、食物繊維、タンパク質、マグネシウムを含んでいます。これらはインスリンの働きを助け、血糖コントロールに寄与する可能性があります。
あるメタアナリシスでは、1日あたり約56gのナッツを食事に取り入れることで、2型糖尿病患者のHbA1cと空腹時血糖値が有意に低下したことが報告されています3。ただし、カロリーが高いため、食べ過ぎには注意が必要です。小腹が空いた時の間食として、ひとつかみ程度が適量です。
| \今だけ500円OFF★まとめ買いクーポン/ ミックスナッツ ナッツ 4種 3種 600g 無塩 有塩 ミックスナッツ ラッキーミックスナッツ プレミアム 380g 送料無料 無添加 アーモンド くるみ カシューナッツ マカダミアナッツ 価格:1,499円~(税込、送料無料) (2025/9/11時点) 楽天で購入 |
ポリフェノールを含む「ベリー類」
ブルーベリーやイチゴなどのベリー類には、「アントシアニン」というポリフェノールの一種が豊富に含まれています。このアントシアニンには、インスリンの感受性を改善し、食後の血糖値上昇を抑える効果があることが示唆されています。
健康な人を対象とした研究ですが、ベリー類を摂取することで、食後のインスリン分泌が抑えられ、血糖コントロールが改善したという報告があります4。デザートとして、ヨーグルトに加えるなどの工夫がおすすめです。
理想的な食事パターン「地中海食」
特定の食品だけでなく、食事全体のパターンを見直すことも非常に重要です。その中で、糖尿病の予防や管理に有効であると広く認められているのが「地中海食」です。
地中海食は、野菜、果物、全粒穀物、豆類、ナッツ類、魚介類、オリーブオイルなどを中心とした食事スタイルです。複数の信頼性の高い研究をまとめた報告によると、地中海食は従来の低脂肪食と比較して、2型糖尿病患者の血糖コントロールをより大きく改善することが示されています5。特定の食品にこだわるだけでなく、バランスの取れた食事パターンを目指すことが、長期的な健康につながります。
専門医の視点からのアドバイス
ここまで科学的根拠に基づいた食べ物を紹介してきましたが、実践する上での注意点がいくつかあります。
- 「これだけ食べれば良い」はない 特定の食品が血糖値に良い影響を与えることは事実です。しかし、それだけを食べていれば糖尿病が治るわけではありません。大切なのは、主食・主菜・副菜をそろえたバランスの良い食事です。
- 食事療法はオーダーメイド 最適な食事内容は、年齢、性別、活動量、合併症の有無などによって一人ひとり異なります。特に腎臓の機能が低下している方は、タンパク質やカリウムの摂取に注意が必要です。必ず、かかりつけの医師や管理栄養士に相談し、自分に合った食事指導を受けてください。
- 運動療法・薬物療法との両立を 糖尿病治療は、食事療法、運動療法、薬物療法の三本柱で成り立っています。食事の改善とともに、ウォーキングなどの適度な運動を取り入れることで、インスリンの効果が高まり、より良い血糖コントロールが期待できます。また、医師から処方された薬は、自己判断で中断しないようにしてください。
- 無理なく続けることが最も重要 厳しい食事制限は長続きせず、かえってストレスになります。まずは、夕食の白米を玄米に変えてみる、間食をナッツにしてみるなど、今日からできる小さな一歩を始めることが大切です。楽しみながら、無理なく続けられる方法を見つけていきましょう。
結語
糖尿病と診断されたことは、これまでの食生活を見つめ直す絶好の機会です。血糖値を下げる効果が期待できる食べ物は、私たちの身近にたくさんあります。本記事で紹介した科学的根拠のある情報を参考に、日々の食事に少しずつ取り入れてみてください。
正しい知識を武器に、前向きに治療に取り組むことが、良好な血糖コントロール、そして合併症の予防につながります。一人で悩まず、医師や管理栄養士といった専門家のサポートも活用しながら、健康な未来への第一歩を踏み出しましょう。
参考文献
- Nutrients. 2020 Jul 17;12(7):2123.
- Nutr J. 2024 Apr 25;23(1):47.
- PLoS One. 2014 Jul 30;9(7):e103376.
- Crit Rev Food Sci Nutr. 2023;63(21):5339-5357.
- Ann Intern Med. 2009 Sep 1;151(5):306-14.
関連記事

この記事を書いた人
都内の総合病院で糖尿病や内分泌疾患を専門に診療している医師です。総合内科専門医/糖尿病専門医/内分泌代謝科専門医/医学博士。年間2000人以上の糖尿病患者さんを診察しながら、学会発表や研究活動も行っています。このブログでは、日々の診療で感じた「患者さんが本当に知りたいこと」「わかりづらい医療情報をわかりやすく伝えること」を大切にしています。正しい知識を知ることが、安心への第一歩になりますように。
【免責事項】本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。
紹介している商品は疾病の診断・治療・予防を目的としたものではなく、効果を保証するものではありません。
使用にあたっては必ずご自身の体調や既往歴を考慮し、必要に応じて医師・薬剤師にご相談ください。