糖尿病は自力で治せる?
糖尿病と診断されたばかりの方の多くが「薬に頼らず自力で治したい」と感じます。実際、インターネット上には「糖尿病が食事で治った」「薬なしで血糖値が改善した」といった情報があふれています。そのため、診断を受けたばかりの方の中には「なるべく薬を使いたくない」「自力で治したい」と考える方も少なくありません。
たしかに、生活習慣の改善によって血糖値が改善するケースは多く存在します。けれども、それは「完治」ではなく「寛解(かんかい)」です。糖尿病は「一度治せばもう再発しない」という性質の病気ではありません。
この記事では、「糖尿病は自力で治せるのか?」という疑問に対して、専門医の視点から科学的根拠をもとにやさしく解説していきます。
なぜ「自力で治したい」と思うのか?

ネット上にあふれる情報
糖尿病に関する情報はインターネット上に大量に存在し、中には「○○茶で治る」「サプリで完治」といった極端なものもあります。こうした情報は不安な患者心理に入り込みやすく、過度な期待を抱かせてしまうことがあります。
薬への抵抗感や不安
「薬に頼りたくない」「副作用が心配」といった理由から、なるべく薬を使わずに治したいという思いを持つ方は少なくありません。とくに初期の段階では、薬=重症という誤解も根強く、心理的ハードルになっています。
前向きな姿勢のあらわれ
生活を変えて健康を取り戻したいという気持ちは、非常に前向きで大切なことです。ただし、その気持ちが「医療を拒否する方向」に向いてしまうと危険です。正しい情報と組み合わせることで、本当の意味での“前向き”になります。
糖尿病とはどんな病気か?
血糖が高いだけではない
糖尿病は血糖値の異常だけでなく、それに伴って起こる全身の障害が問題となる病気です。血管や神経が少しずつダメージを受け、心筋梗塞、脳卒中、失明、腎不全など命に関わる病気につながることもあります。
インスリンの働きの異常
2型糖尿病では、インスリンの効き目が悪くなる「抵抗性」と、インスリンの出が悪くなる「分泌不全」が同時に進行します。特に日本人は分泌能力がもともと弱いため、食生活を少し変えただけでは改善しないこともあります。
生活習慣“だけ”が原因ではない
多くの人が「糖尿病は自己責任」と考えがちですが、実際には遺伝的な要因や加齢、ストレス、他の病気や薬の影響など、複数の因子が関係しています。生活習慣だけでは語れない奥深い病気なのです。
科学的に“治る”ことはあるのか?
ひとたび糖尿病を発症した人は、膵臓のインスリン(血糖値を下げるホルモン)分泌がすでに正常の半分になっているといわれています。なので残念ながら、基本的に糖尿病は治りません。しかし、減量により血糖値が正常化する「寛解」という状態にもっていくことは可能です。
DiRECT試験の知見
英国で行われたDiRECT試験は、過去6年以内に糖尿病を指摘された糖尿病患者を対象とした臨床試験で、体重減少によって多くの肥満の糖尿病患者が1年間、薬なしで正常血糖を維持することができました1。
具体的には
- 5~10kg減量した患者のうち34%
- 10~15kg減量した患者のうち57%
- 15kg以上減量した患者のうち86%
が寛解を達成しました。

発症してすぐの肥満のある患者さんは、体重減少により寛解を目指すことは十分に可能です。
寛解は誰でも可能なのか?
DiRECT試験の対象者は発症早期で合併症のない人たちでした。長年糖尿病を患っている人や、高齢の方には同じような結果が出るとは限りません。また、やせ形の人が無理に減量しても、身体機能の低下や骨粗しょう症など、思わぬ併存症を引き起こすこともあります。寛解は可能すが、誰にでも当てはまるわけではないのです。
日本人の体質の違い
日本人は欧米人に比べて痩せていても内臓脂肪がたまりやすく、膵臓のインスリンの分泌能力も低い傾向があります。そのため、体重を減らしても欧米人ほど明確な寛解に至らないケースも多く、注意が必要です。
食事を変えるだけで“治る”のか?
体重減少で糖尿病が「寛解」することはありますが、以下の方が食事のみで糖尿病を完解に持っていくことはなかなか難しいのが現状です。
- やせ型の方
- 糖尿病になってから長期間たっている方
例えばやせ型のかたが、食事だけで頑張ろうとするあまり、HbA1cが悪い状態が続き、合併症が出てしまう。こういうケースにも我々専門医は多く遭遇します。
あくまで食事・運動・薬物治療の3つがうまく嚙み合ってこそ、良好な血糖管理が達成される。それが糖尿病治療をうまく行うコツです。
“自力で治す”=医療を使わない、ではない
医療との協力こそ「本当の自力」
自分自身で食事や運動を管理することは大切ですが、それを医師や医療チームと相談しながら進めることが、最も安全で確実です。独学で進めて体調を崩すより、医療を活用した「自立」の方がはるかに合理的です。
薬は“最後の手段”ではない
糖尿病治療において、薬は重症時だけに使うものではありません。早めに適切な薬を使うことで膵臓の負担を減らし、将来的に薬を減らせることもあります。薬を使うことは、治療の一部であり「負け」ではないのです。
継続的なフォローが不可欠
たとえ血糖値が一時的に正常化しても、再発リスクは残ります。合併症の早期発見や再発予防のためには、定期的な検査や通院が不可欠です。油断せず継続することが、長期的な健康につながります。
専門医からのアドバイス
完治ではなく「向き合うこと」が大事
糖尿病は、完治を目指すというよりも、日々の生活とどう向き合っていくかが重要な病気です。血糖値の数値に一喜一憂するのではなく、長い目で見て安定した管理を続けていくことが、最善の戦略です。
自分を責めない
「糖尿病になったのは自分のせい」と責めてしまう方が多くいますが、そうではありません。病気を受け入れ、前向きに取り組むことの方がはるかに大切です。自分に優しく、現実的に向き合っていきましょう。
一人で頑張らない
家族や友人、そして医療者といった“支えてくれる人”の存在はとても大きな力になります。孤独に抱え込まず、誰かに相談すること、共有することが、継続的な自己管理を可能にします。
結論:糖尿病は“治す”より“向き合う”病気
寛解はあるが、再発もある
糖尿病は、一定の条件を満たせば「寛解」することがありますが、「完治」ではありません。いつ再発してもおかしくない状態ですので、日々のケアは継続する必要があります。
自分のからだと長く付き合う
糖尿病は、短期決戦ではなく“長期戦”です。自分の体と折り合いをつけながら、無理のない範囲で生活を整えていくことが、合併症を防ぐ鍵になります。
医療を“味方”にするのが本当の自立
医療に頼ることは決して恥ずかしいことではありません。信頼できる医師やチームと二人三脚で歩むことが、最も現実的で、最も安全な「自立した糖尿病管理」です。
参考文献
- Lean ME, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet. 2018;391:541-551.

この記事を書いた人
都内の総合病院で糖尿病や内分泌疾患を専門に診療している医師です。総合内科専門医/糖尿病専門医/内分泌代謝科専門医/医学博士。年間2000人以上の糖尿病患者さんを診察しながら、学会発表や研究活動も行っています。このブログでは、日々の診療で感じた「患者さんが本当に知りたいこと」「わかりづらい医療情報をわかりやすく伝えること」を大切にしています。正しい知識を知ることが、安心への第一歩になりますように。
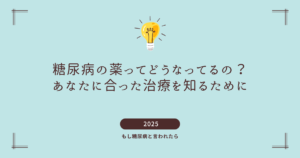
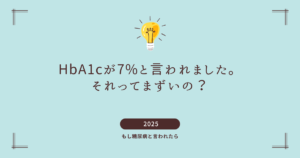
“糖尿病は自力で治せる?” に対して3件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。