はじめて糖尿病といわれたら。専門医がやさしく伝える最初の一歩
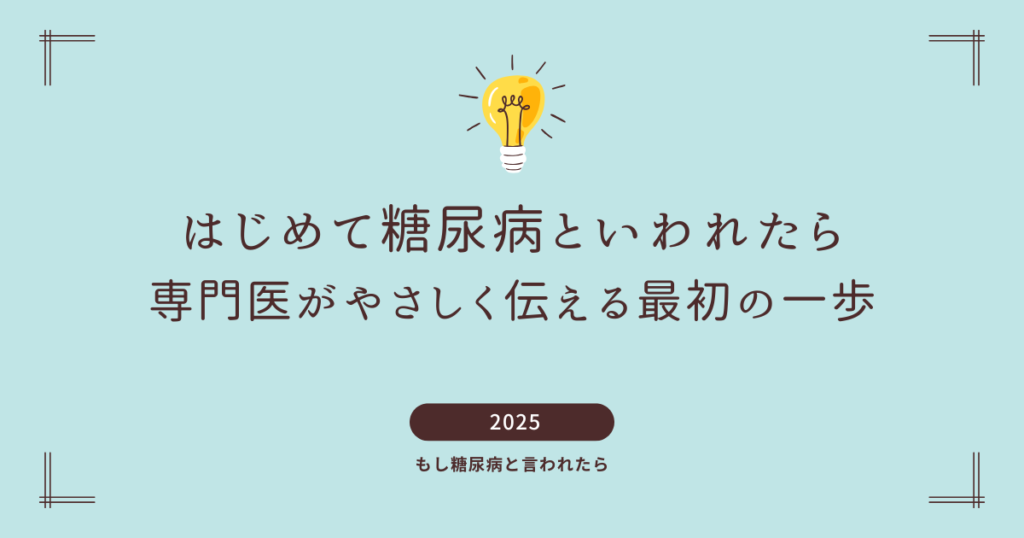
「血糖値が高いですね。糖尿病の可能性があります。」
そう告げられた瞬間、きっとあなた、そしてあなたの大切な人も、不安で戸惑ったことでしょう。
「これからどうなるの?」「何をすればいいの?」「大丈夫なの?」
――そんな気持ちが湧いてくるのは、自然なことです。
でも、どうか知っておいてください。
糖尿病は、正しく理解し、適切に向き合えば、決して恐れる必要のない病気です。
この記事では、糖尿病と診断されたばかりのあなたと、あなたを支えるご家族・パートナー・友人のために、糖尿病の基礎から、治療の選択肢、生活の工夫、そして前向きな未来の歩き方まで、専門医の視点からわかりやすくお伝えします。
このページが、少しでも心を落ち着ける時間となり、「一緒に乗り越えていこう」と思えるきっかけになることを願っています。
この記事では、はじめて糖尿病と診断されたあなたと、あなたを支えるご家族・パートナー・友人のために、
糖尿病の基礎から、治療の選択肢、生活の工夫、そして前向きな未来の歩き方まで、専門医の視点からわかりやすくお伝えします。

糖尿病ってどんな病気?
血糖値が高いってどういうこと?
「血糖値」とは、血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度のことをいいます。
私たちの体は、食事から摂った糖質をエネルギーとして使うために、血液にブドウ糖を送り込みます。そして、それをうまく細胞に取り込ませるのがインスリンというホルモンの役割です。
しかし糖尿病になると、このインスリンの働きが弱くなったり、量が足りなくなったりして、血液中にブドウ糖があふれた状態になります。これが、いわゆる「血糖値が高い」状態です。
血糖値が高いまま続くと、血管や神経、臓器に負担をかけ、さまざまな合併症を引き起こす原因になります。
2型糖尿病と1型糖尿病の違い
糖尿病にはいくつかのタイプがありますが、もっとも多いのが2型糖尿病です。
これは、遺伝的な体質や生活習慣の影響でインスリンの効きが悪くなり、やがて分泌も低下してしまう病気です。日本人の糖尿病の約95%がこのタイプです。
一方で1型糖尿病は、インスリンを作っている膵臓の細胞が自己免疫の反応などで壊されてしまい、インスリンをほとんど分泌できなくなる病気です。年齢に関係なく発症しますが、若い人に多くみられます。

1型糖尿病は現時点ではインスリン注射が必ず必要な病気です。1型糖尿病を治療中の方は、インスリン注射を絶対に中断しないようにしましょう。
この2つの違いを知ることは、治療の方針を理解するうえでもとても大切です。
どうして糖尿病になるの?
2型糖尿病の発症には、遺伝的な体質と生活習慣の両方が関係しています。
たとえば:
- 食べ過ぎや偏った食事
- 運動不足
- 肥満
- ストレス
- 加齢
こうした要素が積み重なると、インスリンの効きが悪くなったり、膵臓が疲れてしまってインスリンの分泌量が減ったりして、糖尿病が進行します。

インスリンの効きが悪くなることを
インスリン抵抗性といいます
一方で、家族に糖尿病の方がいる場合は、体質的に発症しやすいこともあるため、生活習慣を整えることが大切になります。
診断されたときに最初に知っておくべきこと
糖尿病は「怖い病気」じゃない
「糖尿病」と聞くと、合併症やインスリン注射といった言葉が浮かび、不安を感じる方も多いかもしれません。
しかし、糖尿病は正しく理解して、しっかり向き合えば、十分コントロールできる病気です。
たしかに、何もせずに放っておけば、将来的なリスクはあります。でも、いま適切なタイミングで診断を受けたということは、これから先の健康を守るための第一歩を踏み出せたということです。
治療といっても、最初は食事や運動といった生活習慣の見直しが中心になることが多く、無理なく始められることもたくさんあります。
放っておくとどうなるの?
糖尿病の怖さは、「症状があまりないまま進行してしまうこと」にあります。
血糖値が高い状態が長く続くと、血管や神経に少しずつダメージが蓄積され、さまざまな合併症を引き起こします。
代表的なものは以下の3つです:
- 糖尿病神経障害(しびれや痛み、足の壊疽につながることも)
- 糖尿病網膜症(視力障害・失明の原因に)
- 糖尿病腎症(最悪の場合、人工透析が必要に)
こうした合併症は、血糖値をうまくコントロールすることで十分に予防・遅らせることができます。
早くから取り組むことが、将来の安心につながります。
すぐに入院やインスリンが必要なの?
「糖尿病=即入院・注射」というイメージを持っている方も多いですが、実際はそうとは限りません。
ほとんどの2型糖尿病の方は、外来での治療(通院)と生活習慣の改善からスタートします。
薬を使わずにコントロールできる人も多く、入院が必要なケースは、血糖値が極端に高い場合や合併症の精査が必要なときなどに限られます。
また、インスリン注射が必要になるのは、インスリン分泌が大きく低下しているときなど特定の状況であり、最初から全員に必要というわけではありません。
まずは落ち着いて、今のご自身の状態に合った治療を主治医の先生と一緒に、相談しながら進めていきましょう。
これからどう治療していくの?
食事療法:なにをどう変えるの?
「もう一生焼肉やラーメンは食べられないの…?」
そんなことはありません。
糖尿病治療の基本は「食事の見直し」です。といっても、特別な制限を強いられるわけではありません。
大切なのは、血糖値が急に上がりにくい食べ方を意識することです。
たとえば:
- 3食を規則正しく、適量で食べる
- 野菜やたんぱく質を先に食べてから、ご飯やパンを食べる
- 間食や甘い飲み物を控える
こうした工夫だけでも、血糖値は安定しやすくなります。
管理栄養士による個別指導が受けられる場合もあるので、無理なく、長く続けられる方法を見つけていきましょう。

運動療法:どんな運動をどれくらい?
運動は、血糖を筋肉で使う助けをしてくれる重要な治療です。特におすすめなのは、有酸素運動(ウォーキングや自転車など)と、軽い筋トレの組み合わせです。
目安としては:
- 1日20〜30分の軽いウォーキングを週3〜5回
- 1日10分の軽い筋トレを週3回
- 無理なくできる範囲でOK、継続が何より大切です
血糖値の改善だけでなく、ストレス解消や体力維持にもつながるため、治療の柱のひとつとしてとても効果的です。

いきなり頑張りすぎても、続かなければ意味がありません。
「できることを できる時間に 無理のない範囲で」 始めて、
少しずつ習慣化していくことが、長く続けるコツです。
お薬はどんなタイミングで必要?
糖尿病治療では、食事・運動での改善が不十分な場合に、内服薬やインスリン注射などの薬物療法が検討されます。
薬の種類はさまざまで、以下のようなタイプがあります:
- 血糖値の上昇を抑える薬
- インスリンの分泌を助ける薬
- インスリンそのものを補う注射薬 など
治療の選択は、あなたの血糖値の状態や体質、ライフスタイルに合わせて行われます。
決して「すぐに薬が必要=悪化した」という意味ではなく、より良い血糖コントロールを目指すためのひとつの手段です。
日常生活で気をつけたいこと
お酒・たばこ・ストレスとの付き合い方
糖尿病の治療では、日々のちょっとした習慣が血糖値に大きく影響します。
- お酒:適量であれば絶対NGではありませんが、空腹時の飲酒や飲みすぎは低血糖や脂質異常の原因になります。血糖値や薬の種類に応じて調整が必要です。
- たばこ:動脈硬化を進め、合併症のリスクを高めます。糖尿病患者さんにとっては「吸わない」ことが最大の予防策です。
- ストレス:実はストレスがかかると、血糖値が上がりやすくなります。睡眠や気分転換、リラックス法をうまく取り入れましょう。

完璧を目指す必要はありません。「少しずつ整えていく」姿勢で大丈夫です。
検査や通院はどのくらい必要?
糖尿病は、“数値を見ながら調整していく”病気です。自己判断では気づきにくい変化を、定期的な通院で見つけ、対策を立てていくことがとても大切です。
- 通院の頻度:月1回~2ヶ月に1回が一般的(状態により調整)
- 血糖やHbA1cの検査:治療方針を決める基本データになります
- 合併症の検査:定期的な眼底検査、尿検査、神経チェックなども必要です
「今は大丈夫」でも、“今後も大丈夫にしていく”ために通院するという意識でいましょう。
合併症の予防ってどうするの?
合併症は、「血糖値の高い状態が長く続くこと」で進行します。裏を返せば、血糖値をしっかりコントロールすれば、予防できるということです。
大事なポイントは3つ:
- 食事・運動・薬の治療を継続する
- 血圧やコレステロールも一緒に管理する
- 異変がなくても定期検査を受ける
怖い病気と思われがちな合併症ですが、“早くからの行動”が何よりの防御力になります。
前向きに過ごすために
仕事や家庭にどう伝える?
「糖尿病=特別な病気」というイメージが強く、誰かに話すことをためらう方もいます。
でも、正しく理解してもらえれば、協力や配慮を得られることもたくさんあります。
たとえば:
- 休憩時間に軽食をとることの理解
- 通院日の調整
- 飲み会での食事選択のサポート
ご自身が無理をしすぎずに生活を続けるためにも、信頼できる相手にはオープンにすることが前向きな第一歩です。
同じ経験をした人たちの声
「自分だけじゃないんだ」と思えるだけで、心がぐっと軽くなることがあります。
最近では、ブログやSNS、糖尿病患者会などを通じて、糖尿病と向き合いながら前向きに生活している方々の体験談や工夫に触れることができます。
たとえば:
- 食事や運動のちょっとした工夫
- 家族との向き合い方や気持ちの伝え方
- 仕事や育児と両立するための工夫
糖尿病治療はマラソンです。ときには失敗し、迷い、落ち込むこともあるでしょう。しかし仲間がいれば「それでも前を向いて続けているんだ」と勇気をもらえることもあります。
また、地域によっては「糖尿病友の会」などの患者会が開催されており、同じ経験を持つ方々と直接話したり、情報交換をしたりする場があります。
こうした会では、医師・看護師・管理栄養士などの専門職も参加することがあり、安心して学べる機会にもなっています。
患者会については、以下のような団体の情報を参考にできます:
一人で抱えず、同じ道を歩む“仲間”とつながることは、治療を続けるうえで本当に大きな支えになります。
専門医からのメッセージ
糖尿病は、長い付き合いになる病気です。
でもそれは、「自分の体と向き合い、これからの人生をよりよくしていくチャンス」でもあります。
私たち医療者は、あなたの生活に寄り添いながら、無理のない治療と継続の工夫を一緒に考える伴走者でありたいと願っています。
どうか一人で抱え込まず、頼れる人と手を取り合って歩んでいってください。
あなたと、あなたの大切な人が、健康で前向きに日々を過ごせるように――それが私たちの願いです。

この記事を書いた人
都内の総合病院で糖尿病や内分泌疾患を専門に診療している医師です。総合内科専門医/糖尿病専門医/内分泌代謝科専門医/医学博士。年間2000人以上の糖尿病患者さんを診察しながら、学会発表や研究活動も行っています。このブログでは、日々の診療で感じた「患者さんが本当に知りたいこと」「わかりづらい医療情報をわかりやすく伝えること」を大切にしています。正しい知識を知ることが、安心への第一歩になりますように。
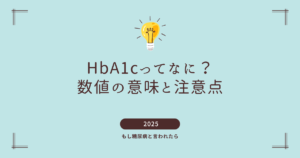
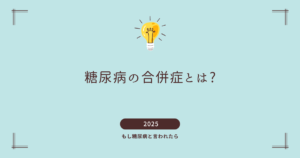
“はじめて糖尿病といわれたら。専門医がやさしく伝える最初の一歩” に対して1件のコメントがあります。